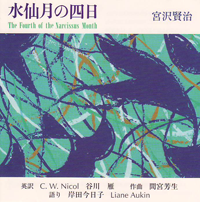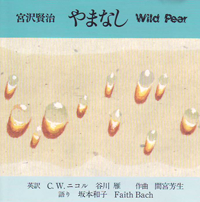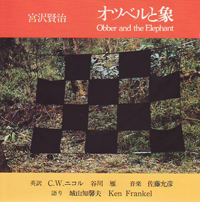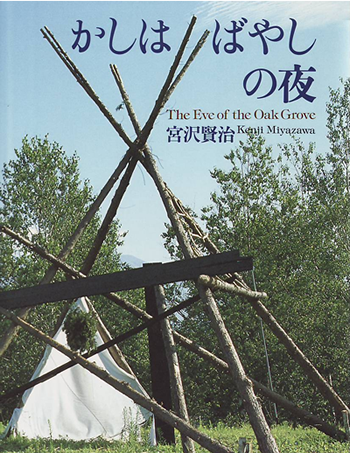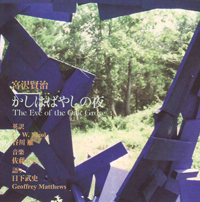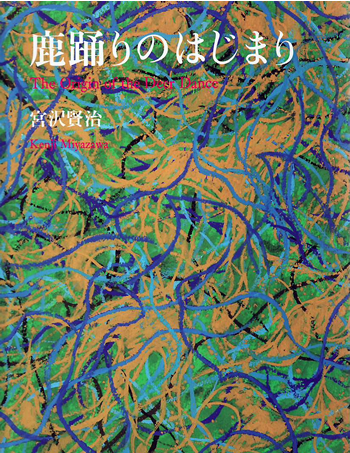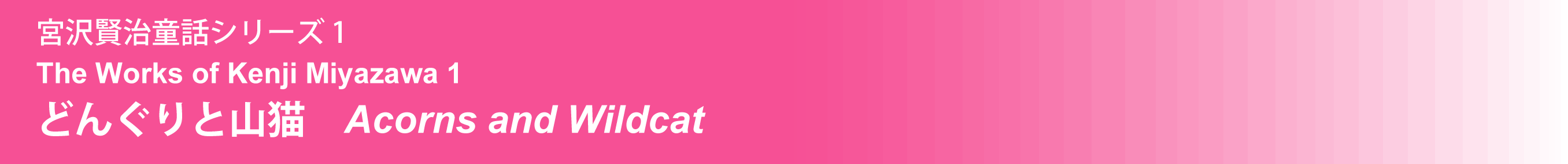
 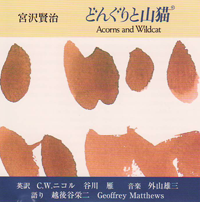
|
賢治の生前に出版されたただ一つの童話集『注文の多い料理店』の巻頭におかれた作品。賢治自身が添えた広告文には「必ず比較をされなければならないいまの学童たちの内奥からの反響です」とあります。CDには日本語版(原作)と英語版を収録、越後谷氏は花巻市の近隣湯田町出身の声優、Matthews
氏は録音のためにロンドンからお招きしました。絵本は李禹煥氏による墨書ふうの抽象画でつくられています。
[本文より] |
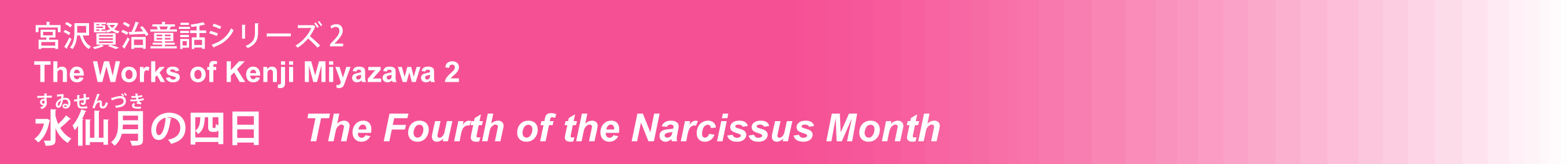
|
絵本: 高松 次郎
|
賢治童話のなかでももっとも人気の高い作品の一つ、しかし水仙月は何月と聞かれて即答できるひとは多くないでしょう。答えは四月、冬の間に焼かれた炭を父親といっしょにそりで町まで運んだ少年は、一足さきに帰る途中、春の雪嵐に巻きこまれてしまいます。おそいかかる吹雪のさまが比類なく美しいことばでつづられたこの物語は、賢治の天才をあますところなく示しています。
[本文より] |

|
絵本: 金 昌烈
|
小さな谷川の底をうつした幻燈という設定は、草創期の新芸術、映画に寄せる賢治の関心の深さをうかがわせます。子どものカニの小さな目玉が水中カメラになって、ふりそそぐ光とゆらめく影、泡や魚、天井をすべる樺の花びらをうつしだします。音楽は制作当時来日中だったアフリカの打楽器奏者カクラバ・ロビ氏によるコギリ(シロフォンに似た楽器)の演奏をモチーフに、間宮芳生氏がアレンジしました。
[本文より] |

|
絵本: 菅 木志雄 |
聖なる白象とやり手の農場主オッベルの物語は、シャカ誕生の地に近いインドとネパールの国境あたりを舞台にしていると考えられます。ですから、語り手の牛飼いのかう牛もおそらくこぶ牛、しかしそんなふうに地籍さがしをつづければ、このお話がアジアや仏教におさまりきれない広さと多様さをもつことにすぐ気づくことになります。英語は牛飼いの語りにふさわしいように書かれ、また読まれています。
[本文より] That fellow Obber is guite some guy. オツベルときたら大したもんだ。 He's got six of them, rice threshers, all set up and going run-run-run-run-run-run! A terrible racket. 稲扱(いねこき)器械の六台も据(す)ゑつけて、のんのんのんのんのんのんと、大そろしない音をたててやつてゐる。 Sixteen farmers, right red in the face, are working those pedal machines, 十六人の百姓どもが、顔をまるつきりまつ赤にして足で踏んで器械をまわし、 making their way through a mountainous pile of rice sheaves, one bundle after another. 小山のやうに積まれた稲を片つぱしから扱(こ)いて行く。 Pedal-toss, pedal-toss, there goes the straw behind them, piling up again in a new mountain. 藁(わら)はどんどんうしろの方へ投げられて、また新らしい山になる。
|
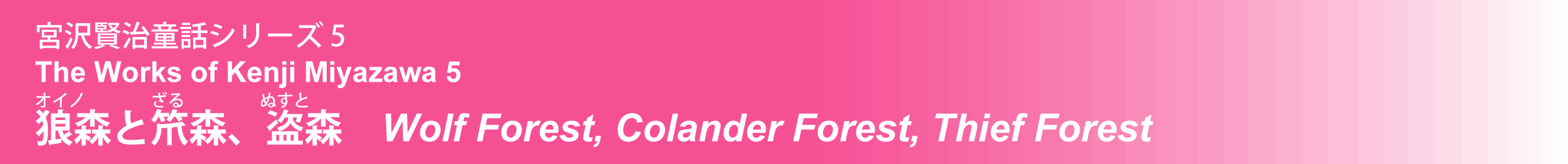
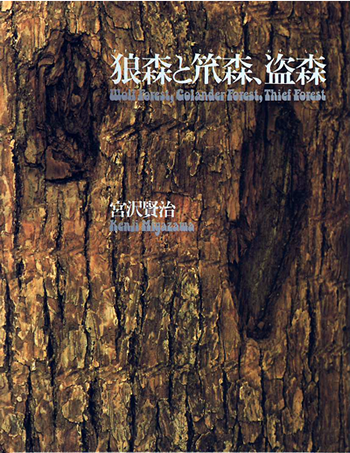 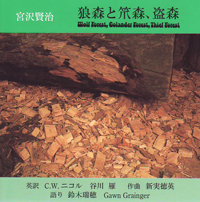
絵本: 江口 週 |
原野への入植は辛苦にみちたものですが、寒冷地ではなおのこときびしい。賢治がこの物語につけた広告文には「人と森との原始的な交渉で、自然の順違二面が農民に与へた永い間の印象です」とあります。順違とは、自然の恵みと過酷さといいかえることができるでしょうか。年ごとの収穫の祭りを幼年の眼がどのように見たか、過酷な暮らしの実相が甘美な記憶につつみこまれる賢治の傑作童話の一つです。
[本文より]
|

 
絵本: 福岡 道雄 |
「うろこぐもと鉛色の月光、九月のイーハトヴの鉄道線路の内想です。」 賢治がこの物語にあたえた広告文はこのように短いものです。新文明・鉄道線路の内想とは不可解ですが、ここに登場する恭一少年がどうやら思春期の入口にあることを考えれば、内想は少年の内面でもあるらしいことがわかります。ドッテテではじまるでんしんばしらの行進曲は、賢治の残した譜面を尊重してアレンジされています。
[本文より] |

|
絵本: 斎藤 義重 |
お盆だというのに畑仕事をしている清作は、どこからともなく現れた画かきにつれられて、柏ばやしの夏のお祭りにまぎれこみます。ふたりを結びつけたものが歌なら、お祭りも歌合戦、その合間には柏の木大王と清作のあいだに険悪かつユーモラスな対話がかわされます。絵本は夏の高原で、女子高生たちの制作を斎藤義重氏が指導された、その成果をもとに構成されています。
[本文より] |

|
絵本: 高松 次郎 |
足のけがを癒すために山の湯へむかった青年嘉十は、六ひきばかりの鹿の群に遭遇します。魅入られたようにその姿を見つめる嘉十の耳にやがて鹿たちの話すことばが聞こえてきます。鹿と人とのあいだに異種間交流はなりたつのでしょうか。太陽に向いてならび、それぞれ歌をうたった鹿たちは、求愛の季節のおとずれにしたがって、ちりぢりになっていきます。佐藤慶氏の方言による表現をお楽しみください。
[本文より] |
賢治童話シリーズ9〜15はこちら